戸所
【読み】とどころ
【全国順位】
11,188位
【全国人数】
およそ590人
由来解説
戸所さんの多い地域 TOP5
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 東京都 | およそ230人 |
| 群馬県 | およそ180人 |
| 神奈川県 | およそ50人 |
| 埼玉県 | およそ40人 |
| 千葉県 | およそ30人 |
| 市区町村 | 人数 |
|---|---|
| 群馬県前橋市 | およそ120人 |
| 東京都立川市 | およそ70人 |
| 東京都国立市 | およそ30人 |
| 東京都小笠原村 | およそ30人 |
| 神奈川県鎌倉市 | およそ20人 |
戸所さんの比率が多い地域 TOP5
| 都道府県 | 比率 |
|---|---|
| 群馬県 | 0.00958% |
| 東京都 | 0.00176% |
| 滋賀県 | 0.00076% |
| 埼玉県 | 0.00056% |
| 神奈川県 | 0.00055% |
| 市区町村 | 比率 |
|---|---|
| 東京都小笠原村 | 1.028% |
| 群馬県利根郡川場村 | 0.136% |
| 群馬県利根郡片品村 | 0.102% |
| 群馬県吾妻郡草津町 | 0.073% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 0.053% |
戸所さん有名人アクセスランキング TOP10
| 名前 | 生年月日 | ジャンル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 戸所 隆 | 1948年 | 研究者 | 地理学者 |
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。

| 戸所さん みんなの名字の由来 |
|---|
|
群馬県には「とどころ」と読む名字の種類が多い。 戸所 前橋市に多い 外処(外處)高崎市に多い 外所 高崎市に多い 都所 東吾妻町に多い |
|
【投稿日】2024/06/17 23:26:13 【投稿者】ちば子さん |
| 【戦国の剣聖と戸所一族】 戸所甚内・甚兵衛親子が名を連ねる長野氏家臣録「永禄元年軍評定着到帳」(1558)が記された9年後、その拠点・箕輪城が武田信玄に落とされ、長野氏は滅亡した。「戦国の剣聖」といわれ、柳生石舟斎に新陰流を伝授した上泉伊勢守信綱も箕輪長野氏の武将で、武田信玄の箕輪城攻めでは戸所甚兵衛を惣領とする戸所一族と共に城内に立て籠もり、武田軍と戦っている。 信綱は「兵法三大源流」とされる陰流、神道流、念流を修め、独自に「新陰流」を大成した。箕輪の道場には各地の剣客が集まり、盛時の門人数は1500人を超えたといわれる。戦乱の世で「命のやりとり」を日常とする戸所一族も信綱から手ほどきを受けていたと思われる。 箕輪城陥落後、武田信玄は勇猛で知られる百戦練磨の長野軍団の落武者たちを生け捕りにし、戸所甚兵衛を含む約200人を家臣・内藤修理の直属軍団に組み込んだ。一方、信綱は武田氏への仕官を断り、信玄の許しを得て諸国放浪の旅に出る。のちの徳川将軍家の兵法指南役・柳生宗矩の父、石舟斎はこの諸国放浪中の信綱に弟子入りし、新陰流二代目の印可状を与えられ、世にいう「柳生」新陰流を創始した。(「甲陽軍大全」「箕郷町誌」参照) |
|
【投稿日】2017/12/03 07:28:12 【投稿者】inazumaさん |
| 【戸所惣領家の足跡】戸所一族が長野氏の直属家臣となったのは長野業政の父・憲業が榛名山東麓の要害の地に箕輪城を築城した永正9年(1512)以降のことと思われる。長野氏はかつて石井姓を称し、上野国の国衙(朝廷任命の国司の役所)の官人(行政官)を代々勤めていたが、室町中期に国衙領の群馬郡長野郷に移り、姓を「長野」と改め、豪族として同地に土着。関東の内乱が続く中で長野郷一円の地侍を含む大小の土豪を被官化し、上野守護代の総社長尾氏などと姻戚関係を結んで急速に勢力を拡大した。この過程で戸所一族も所領を守るため長野氏の家臣団に組み込まれたとみられる。 このころ、伊豆を領国化した伊勢氏が相模一国(神奈川県)を経略し、名字を「北条」に改め、小田原城を拠点に関東への侵攻を開始している。天文7年(1538)、北条氏は鎌倉公方の嫡流を名乗る古河公方・足利晴氏から「関東管領」職を与えられ、鎌倉府以来の関東管領家・山内上杉氏との抗争が本格化。長野氏の当主・長野業政は山内上杉氏の後ろ盾を得て、「箕輪衆」と呼ばれる在郷武士団を束ね、総社長尾氏とともに上杉方の重鎮として活躍するが、天文21年(1552)、北条氏康が上杉氏の拠点・平井城(群馬県藤岡市)を攻め落とし、当主の上杉憲政は長尾景虎(のちの上杉謙信)を頼って越後に没落した。 景虎は翌年、武田晴信(のちの武田信玄)と第一次川中島合戦を戦うが、その前後に相模北条氏、甲斐武田氏、駿河今川氏の「甲相駿三国同盟」が成立。以後、北条・武田連合軍と、上杉憲政を擁する長尾景虎との上野、信濃両国の覇権を巡る熾烈な戦いへと発展する。この時代状況のさ中、戸所甚内、戸所甚兵衛が登場する「永禄元年軍評定着到帳」(1558)が作成されたのである。 ちなみに、箕輪長野氏は直属家臣(旗本直臣衆)を領内要所の「内出」と称する直轄地に居住させており、戸所一族も長野業政の時代に、長野氏が領有していた前橋市元総社のかつて「字中内出」と呼ばれた地域に移住させられたとみられる。ここは箕輪城の東の防衛線・利根川の右岸にあり、近くには上野守護代・長尾氏の居城「蒼海城」があった。移住地には屋敷のほか、多少の田畑が与えられたと思われるが、日常はほぼ長野氏の戦闘要員に特化。上豊岡町にある「本領」は耕作民にゆだね、地代を徴収するだけの関係になったとみられる。 西上野は戦国大名の上杉、北条、武田3氏の三つ巴の覇権争いのただ中にあり、長野氏が武田信玄に滅ぼされるまで、戸所一族は元総社の移住地を拠点に戦いの日々を送った。 箕輪落城後、戸所惣領家は武田信玄の家臣・内藤修理の直属軍団に組み込まれ、以後は内藤軍団を中核とする箕輪衆として戦国時代を駆け抜ける。武田氏の滅亡後、箕輪衆は勝者の織田信長の支配下に入り、信長が「本能寺の変」で殺害されたあとは、上野国に攻め込んだ北条氏の軍門に降った。その北条氏は天正18年(1890)、豊臣秀吉の小田原征伐で倒れ、秀吉に関東八カ国(関八州)を与えられた徳川家康が重臣・井伊直政を初代箕輪藩主(のち高崎藩主)に据えると、多くの箕輪衆は戸所惣領家を含め井伊直政の家臣となった。敗者が勝者に従属するのは戦国時代の習いであり、さもなければ滅びるだけだった。 この時、「元総社」にある戸所惣領家の屋敷と付属田畑は、所在地周辺が箕輪藩の飛地領とされたため、そのまま安堵されたが、支配領域外となった上豊岡町の所領は没収され、戸所惣領家は藩主に俸禄を支給される「扶持米取り」になったとみられる。 慶長5年(1601)、井伊直政は近江に領地替えとなるが、戸所惣領家は東隣の総社藩に移籍し、直政配下の武将から一躍、総社藩主の座に就いた秋元長朝に仕えた。長朝が大名に出世したのは慶長5年(1600)の「関ケ原の合戦」の際、徳川家康に敵対していた会津・上杉景勝(上杉謙信の養子)を調略し、参戦を阻止した功績による。ちなみに、直政の領地替えの際、戸所惣領家は2つに割れ、分家は井伊氏の陪臣として近江に移っている。 総社藩士となった惣領家は以後、秋元氏家臣として藩主の転封に従い、甲斐谷村藩、武蔵川越藩、出羽山形藩、上野館林藩へと移動を繰り返した。戸所家の系譜がはっきりと辿れるのは秋元氏の「分限帳」(家臣録)が残るこの総社藩以降のことである。 秋元長朝は上野守護代だった総社長尾氏の蒼海城(前橋市元総社)を廃却し、利根川右岸に総社城(前橋市総社)を築いて城下町を移した。江戸初期の「総社城の図」(秋元氏家臣杉本孟恭作図)に描かれた町屋には「戸所六右衛門」、「戸所源蔵」の名が見える。この「六右衛門」は戸所家惣領の字名(あざな。通称)であり、年代的にみて「戸所六右衛門甚兵衛」の可能性もある。 秋元氏は長朝から数えて11代目の館林藩主・秋元礼朝の時代に明治維新を迎えた。明治4年(1871)の「廃藩置県」の際に館林県(旧館林藩)が明治政府に提出した士族禄高取調帳に「士族 戸所文平」、「士族 戸所半平」と記されており、戸籍簿にある筆者の高祖父の氏名と重なる。 「戸所文平」は「戸所半平」の父で、安政2年(1855)、館林藩河州郡奉行・独礼席の職にあった「戸所六右衛門」のことである。独礼席は藩主と単独面会できる身分であり、河州郡奉行は秋元氏の飛地領である河内3郡37村(現在の大阪府松原市と堺市の一部。1856年の石高は2万7131石、家数4076件、惣人数1万8391人)を差配した。当時の古絵図には、館林城大手門内の大名小路付近に「戸所文平」名義の屋敷が見える。これが戦国乱世を駆け抜け、江戸時代、そして明治維新へと生命をつないだ戸所惣領家の足跡であり、少数一族とはいえ同根の戸所家はこの過程で群馬、滋賀、山梨、埼玉など各地に根を張り、「戸所」姓を今に伝えているのである。 |
|
【投稿日】2017/12/03 07:25:32 【投稿者】inazumaさん |
| 戸所は戦国時代、群馬県の榛名山南東麓に発祥した地侍の一族であり、「戸所」姓はこの一族固有のもの。全国に散在する戸所家はすべて同根である。 古い史料(群馬町足門・岸家文書)では西上野の有力国衆・箕輪長野氏の長野業政家臣録「永禄元年正月廿九日改軍評定着到帳」(1558)に「戸所甚内」、「戸所甚兵衛」の名が記されている。 戸所一族が長野氏の直属家臣団(旗本直臣衆)に組み込まれたのは戦国時代だが、それ以前は室町中期、上野国西部の片岡郡内にあった鎌倉円覚寺領の荘園(豊岡荘)の経営を請け負う名主(みょうしゅ)か、荘官だったと思われる。円覚寺文書によると、貞治3年(1364)に初代関東管領(鎌倉公方足利氏の補佐役。鎌倉公方は室町幕府が関東支配のため設置した鎌倉府の長官)・上野国守護の山内上杉憲顕が烏川右岸の守護領の一部、「上野国八幡庄之内鼓岡村半分」を寄進したとあり、「鼓岡」すなわち「豊岡」荘の領域は現在の高崎市上豊岡町一帯だったとみられる。ちなみに、この地は10世紀前半に編纂された「倭妙類聚抄」の「片岡郡長野郷」にあたり、烏川左岸の「群馬郡長野郷」と烏川をはさんで隣接し、当時は両郷を総称して「長野郷」と呼んでいた。 名主(あるいは荘官)の戸所惣領家は豊岡荘の一隅に屋敷と租税免除の「給田」を与えられたが、やがて上野国全土を巻き込む関東管領上杉氏と鎌倉公方足利氏との27年間に及ぶ下克上の内乱(享徳の乱、1454)が起こり、荘園制度が瓦解する中で惣領家は武装化し、地侍(土豪)に転身。給田周辺の荘園請負地を私領化し、その地形の特徴を取って「戸所」の名字を名乗った。 「戸」とは「水流の出入りするところ」、「所」とは「領有する土地・地域」を意味する(広辞苑)。この地は群馬、長野県境の鼻曲山(標高1655㍍)に源を発する烏川と、両県境の碓氷峠(標高960㍍)が源の碓氷川との合流点(高崎市役所北西約700㍍)の北西約3.5㌔にあり、明治初期に編纂された「上野国郡村誌」には「水利便ナレドモ毎歳水害ヲ免カレス」とある。この地形を名字にとることで、自領の領域を内外に明らかにし、「一所懸命」に守り抜く決意を込めたのであろう。 なお、戸所一族は箕輪落城後、武田信玄の家臣・内藤修理の直属軍団に組み込まれ、武田氏滅亡後は北条氏に仕え、北条氏没落後は「徳川四天王」の井伊直政(初代箕輪・高崎藩主)の配下に入った。その後、井伊直政の転封(領地替え)に伴って一族は近江(滋賀県)に移るか、隣の総社藩主・秋元氏の家臣となるか、在地で帰農した。現在も前橋市の総社地区には約20軒の戸所家が在住している。総社藩士となった戸所惣領家は藩主・秋元氏の転封で甲斐谷村藩、武蔵川越藩、出羽山形藩、上野館林藩と各地を転々。幕末の館林時代は河州郡奉行(河州は秋元氏の飛地領の河内3郡37村=現在の大阪府松原市と堺市の一部。1856年の石高は2万7131石、家数4076件、惣人数1万8391人)の要職にも就いた。当時の古絵図には館林城大手門内に「戸所文平」と書かれた大きな屋敷も見える。 |
|
【投稿日】2017/11/08 17:59:45 【投稿者】inazumaさん |
| みんなの名字の由来 投稿 |
|---|
「みんなの名字の由来」に書きこむには、ログインが必要です。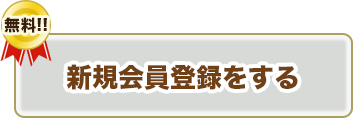
|
同姓同名検索はこちら
戸所さんと相性のいい座席を診断!
戸所さんと気になるあの人の相性を診断!
個別に家系図を知りたい方はこちら
スマートフォン専用の検索はこちら
戸所さんプレミアム会員とは
すでにプレミアム会員の方へ
| 戸所さん みんなの家紋のはなし | |
|---|---|
まだ戸所さんの「みんなの家紋のはなし」がありません。

|
|
| 戸所さん名字伝言板 |
|---|
|
【語られているテーマ】名字について情報がほしいです 【限定地域】群馬県 【語りたい名字または名前】戸所さん ※名字情報ある方のみ 探してます 続きはこちら |
|
投稿者:ちいさん 最新投稿日時:2012/07/03 09:58:28
|
※名字の順位・人数は2025年10月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※名字由来netは政府発表統計や独自調査により得られたデータから、日々変化する日本人の名字の人数を日本で唯一算出しております。
※名字の推計人数は四捨五入して掲載しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。また、推計人数が少ない名字につきましては、一律「およそ10人」としています。
※名字の専門企業が算出している日本唯一の名字オリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々はこちらよりお気軽にご相談ください。
※解説欄に「詳細不明」等と記載されている場合でも、「読み」や「有名人情報」が更新された際「新着・更新」名字欄に掲載されます。
※名字の情報を欲しい方は「情報求む」ボタンを押してください。「情報求む」欄には最新10件のみ表示されますので、定期的に確認いただき更新されることをお勧めします。
名字について詳しい情報をお持ちの方は、「名字の情報を送る」より名字の情報をお書きのうえ、送信ください。お送りいただいた情報はルーツ製作委員会にて精査し、名字の解説として掲載させていただくことがあります。
名字検索
最近検索された名字
蕚 藤田 籠畑 梅実 才野 村垣 鼠田 涌波 底押 永広 冨内 末竹 土成 秋田 神丸 矢ノ中 河俣 今長 要石 水安 水和 時庭 住徳 南條 幸脇 首道 魚住 国永 竹並 足洗 二子石 根市 天峰 土屋 鷲平 畔見 用皆 菊光 長濵 名原 佐林 摺出寺 仙崎 濡髪 樽 佛田 高邑 芳野 山岸 山景 杷野 金丸 鳩山 竹箇平 新熊 光富 徳留 島袋 上ノ段 恩知 徳尾 目賀田 強矢 生見 初沢 片峰 張丁 市上 石室屋 吉岡 蝦 裏加 化生 出津 鑪 水野 仙河 久家 常松 櫛渕 貞山 久井 池末 金氏 江 罍 飯牟禮 随念 碓氷 濱根 深江 利一 飯郷 本影 姉歯 宗像 上之浜 岡松 園城寺 中條屋
家紋検索
当サイトは多くのユーザー様に広くご自分や身近な方の名字の由来を知って頂くことを目的としておりますので、「情報の流用や加工を目的とした不正なアクセス」「他の文献等の内容を無断転載する」「不正なIPアドレス」
「同一人物が他人を装い、いくつものアカウントを使用し、不正なアクセスや当サイトに混乱をきたすような行為」「他サイトなどで根拠のない誹謗中傷などが発見された場合」
など左記はごく一部ですが、利用者に混乱をきたすと判断された場合は、データ保護の観点により、アクセス禁止措置、更に迷惑行為と判断し、法的措置を取らせていただく場合がございますので、ご了承ください。
取材等につきましてはこちらからご連絡ください。

 「連濁(れんだく)」について
「連濁(れんだく)」について

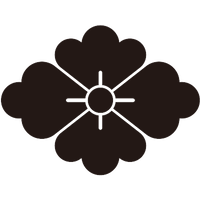 花菱
花菱

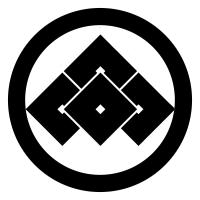

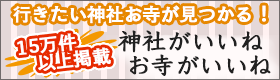





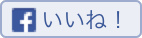

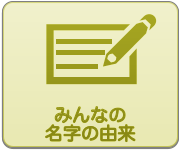






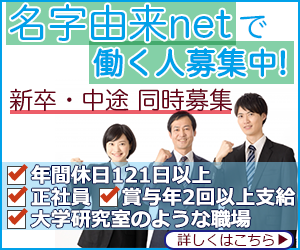
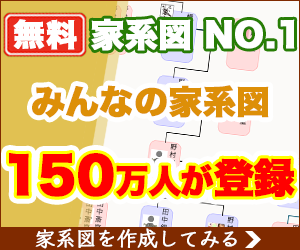

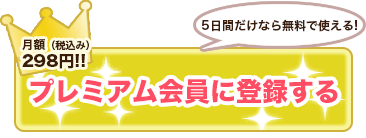
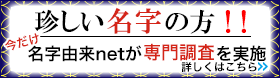
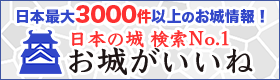
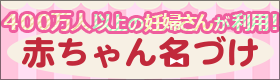
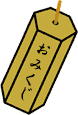

 全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
珍しい名字について語りまし…
 全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
名字について情報がほしいで…
 全国/
その他
全国/
その他


